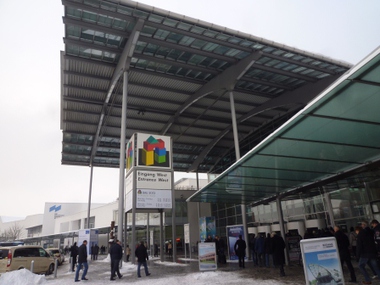ドイツの窓
意外と気が付いていないのが窓の役目の中の換気、を行うということです。
そして、住宅の重要な機能の中で、「換気」をおこなうのにもっとも最適なのがドイツを代表する窓、「ドレー、キップ」なのです。わたしはブログのなかで過去何度か書きましたが、この窓はほんとうにすばらしい。
先日、森の窓から、4トンウィング車ほぼいっぱいの木製窓が出荷されました。明石市にお住いの女性設計士さんの
自宅一棟分ですが窓はほとんど「ドレー、キップ」でした。依頼をうけて相談にうかがってからおよそ1年、途中工事の遅れで3,4か月の停滞はありましたが、ようやく納品となりました。
この仕事は、わたしにとって久しぶりに印象に残った仕事で、ずいぶんと勉強にもなりました。電話やFAXでのやり取りは数十回におよび、普段気の付かない素朴な問題を再認識させられたしごとでもありました。
そんな中、お客様から再認識させられたのがドレー、キップ窓の「換気窓」としての役割でした。木製窓の換気機能についてはこののちも重要なテーマとして取り上げていくつもりです。
そして、住宅の重要な機能の中で、「換気」をおこなうのにもっとも最適なのがドイツを代表する窓、「ドレー、キップ」なのです。わたしはブログのなかで過去何度か書きましたが、この窓はほんとうにすばらしい。
先日、森の窓から、4トンウィング車ほぼいっぱいの木製窓が出荷されました。明石市にお住いの女性設計士さんの
自宅一棟分ですが窓はほとんど「ドレー、キップ」でした。依頼をうけて相談にうかがってからおよそ1年、途中工事の遅れで3,4か月の停滞はありましたが、ようやく納品となりました。
この仕事は、わたしにとって久しぶりに印象に残った仕事で、ずいぶんと勉強にもなりました。電話やFAXでのやり取りは数十回におよび、普段気の付かない素朴な問題を再認識させられたしごとでもありました。
そんな中、お客様から再認識させられたのがドレー、キップ窓の「換気窓」としての役割でした。木製窓の換気機能についてはこののちも重要なテーマとして取り上げていくつもりです。